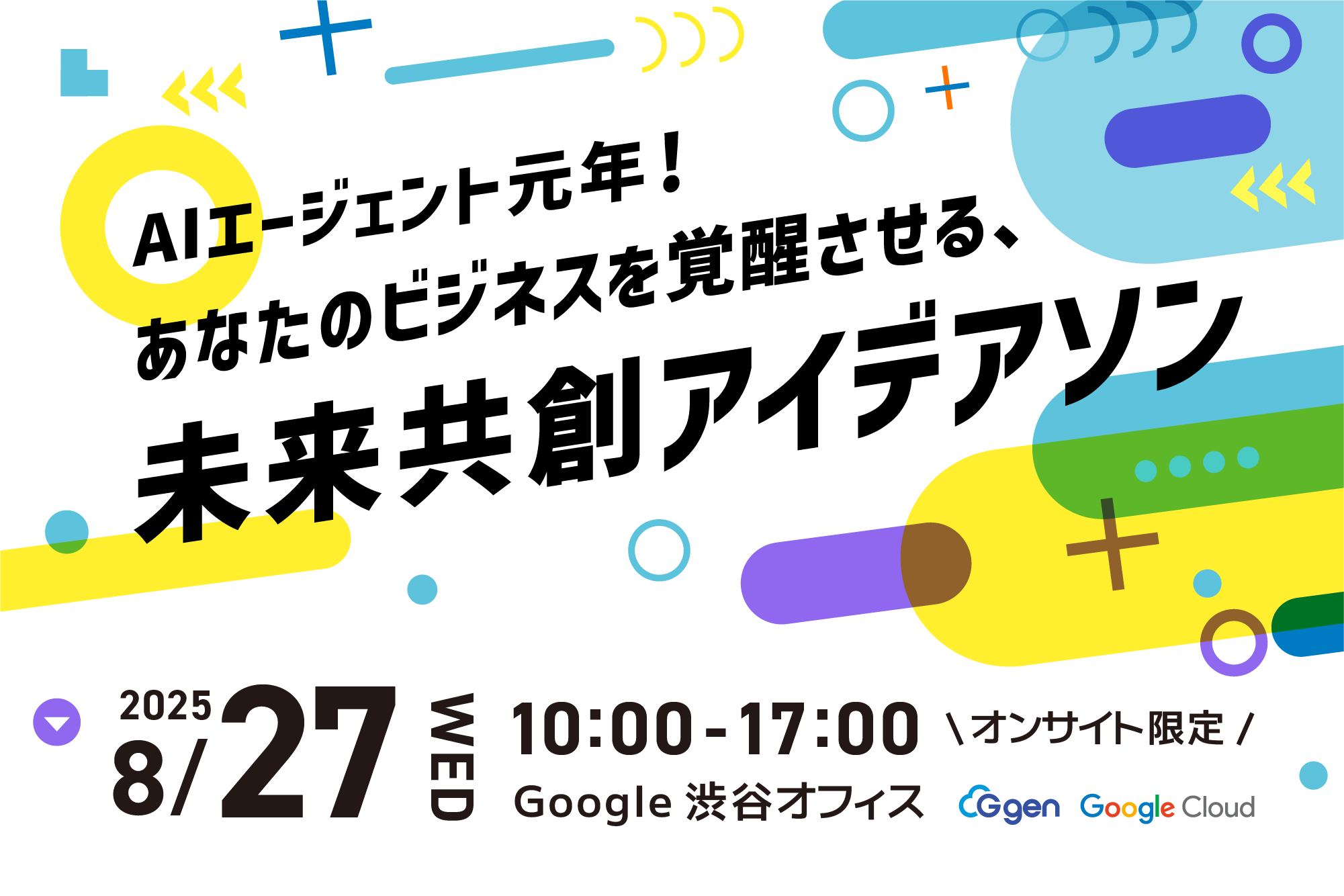内製化とは?メリット・デメリット、実践すべきかの判断ポイントを解説
- 内製化支援
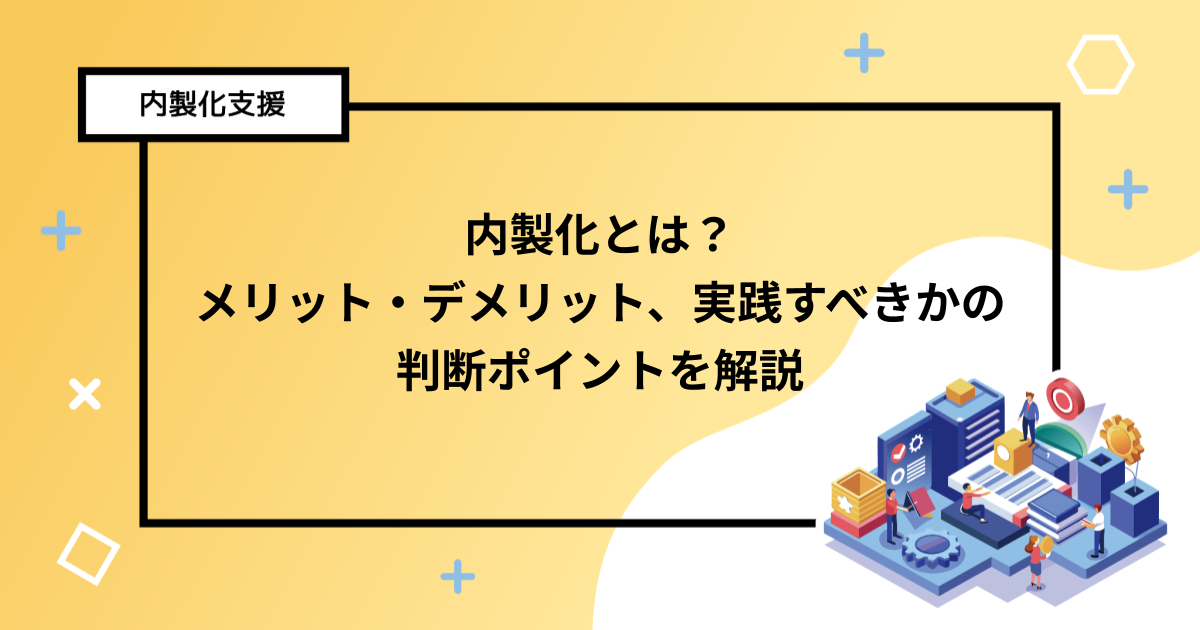
昨今、システムの内製化が大きな注目を集めており、実際に多くの企業がシステムの開発・運用などを内製化し、自社の業務効率化や生産性向上に繋げています。
しかし、内製化という言葉を聞いたことがあっても、具体的な内容について理解していない方も多いのではないでしょうか?本記事では、内製化の意味やメリット・デメリットに加えて、内製化が向いている企業・向いていない企業の特徴など、実践すべきかの判断ポイントとあわせてご説明します。
内製化とは?
内製化とは、外部ベンダーの力を借りて運用しているシステムを自社内での開発・運用に移行することを意味します。また、運用方法を切り替えるだけではなく、他社システムの利用をやめて、代わりにシステムを自社開発することも内製化の一種です。
これまで、日本企業はシステム運用を外部ベンダーへ一任することが一般的でしたが、障害発生時にベンダーへ連絡を取らなければいけなかったり、システムの仕様的な問題からカスタマイズに制限がかかったりするなど、多くの場面で不都合が発生していました。
現在、このような課題に対する解決手段の一つとして内製化が注目されており、多くの企業が内製化を実現するために様々な取り組みを行っています。詳しくは後述しますが、システムを内製化することで、企業は様々なメリットを享受できるため、自社のビジネスを成長させるうえでは、内製化が重要な要素の一つになると言えるでしょう。
内製化の 3 つのメリット
企業が内製化を実現することで、どのような恩恵を受けられるのでしょうか?本章では、内製化の代表的なメリットを 3 つ解説します。
1)外部委託コストを削減できる
システムを内製化するメリットの一つとして、外部委託コストを大幅に削減できる点が挙げられます。外部ベンダーに開発や運用を依頼する場合、契約費用や追加改修の度に発生するコストがかさむことがあります。
一方、社内のリソースを活用してシステムを構築すれば、一定の初期投資は必要になりますが、長期的な目線ではコストの最適化が期待できます。特に、自社の業務に精通したエンジニアが開発を担当することで、無駄な仕様や過剰な機能を省き、必要な部分に集中した効率的な開発が可能になります。
2)業務効率化に直結する
内製化されたシステムは、自社の業務フローや特性に合わせてカスタマイズできる点が強みの一つです。既存のパッケージソフトや外注システムでは、業務をシステムに合わせて見直す必要がありますが、内製化においてはその必要はありません。
さらに、システム改修や新機能の追加が必要なシーンでも、様々な作業を社内で迅速に対応できるため、結果として組織全体の業務効率化に繋がります。また、現場からのフィードバックを直接取り入れられるため、ユーザビリティの高いシステムを実現できる点も大きな魅力だと言えます。
3)市場競争力の強化に繋がる
内製化されたシステムは単なる業務サポートのツールに留まらず、企業の市場競争力を高めるための重要な戦略的資産となり得ます。例えば、競合他社にはない独自の機能やサービスを迅速に開発することで、競合他社との差別化に繋がります。
また、システムの改修・改善をスピード感をもって行うことで、市場の変化にも柔軟に対応できます。このように、情報技術が事業競争の鍵を握る現代において、内製化は企業のイノベーションを促進するための重要な役割を果たしているのです。
内製化の 3 つのデメリット
内製化には様々なメリットがありますが、同時に注意しなければいけないデメリットも存在します。本章では、システム内製化のデメリットを 3 つご紹介します。
1)IT 人材の採用・教育にコストが掛かる
システムを内製化するためには、 IT 人材の採用が必要不可欠になります。しかし、近年の IT 人材不足により、優秀なエンジニアを確保するためには、高額な報酬や採用活動の強化が求められます。
また、新たに採用した人材を自社の業務に馴染ませ、スキルを育成するためには一定の時間とコストを要します。さらに、既存社員に対してもスキルアップを目的とした研修やトレーニングを実施する必要があるため、人的リソースの投資は避けられないと言えます。
2)設備投資やシステム運用のコストが発生する
企業が内製化を進める上では、サーバーやネットワーク機器をはじめとした IT インフラの整備が求められます。また、クラウドサービスを利用する場合、継続的なランニングコストやデータ管理コストが発生することが一般的です。
さらに、システムの運用・保守を継続的に行うためには、専任チームの結成や外部ツールの導入が必要であり、その運用コストも忘れてはいけないポイントになります。このように、設備投資やシステム運用に関するコストが発生する点は、企業の内製化を阻む壁の一つになり得るでしょう。
3)プロジェクト開始直後は業務効率が低下する可能性がある
内製化されたシステムは自社に最適化されていることが大きなメリットである一方で、導入初期にはトラブルや調整が発生しやすいため、この点には注意が必要です。特に、開発の初期段階では想定外の課題が出てくる傾向にあり、日々の業務プロセスにおいて混乱を引き起こすリスクがあります。
また、新システムへの移行や利用者の習熟が進むまでの期間は、社員が旧システムとの併用や新しい操作に戸惑い、業務効率化が一時的に低下することも考えられます。ただし、中長期的な視点で見れば、内製化による効果は非常に大きいため、数年後を見据えて計画的にプロジェクトを進めることが大切です。
内製化が向いている企業と向いていない企業の特徴
企業がビジネス成長を実現するうえで、内製化は有効な選択肢の一つになりますが、すべての会社が内製化を実践すべきだとは言えません。本章では、内製化が向いている企業と向いていない企業の特徴について解説します。
内製化が向いている企業
自社独自のサービスやプロダクトを持ち、それらを強化するための技術力を社内に蓄積したいと考えている企業の場合、内製化はとても有効な選択肢になります。このタイプの企業は、競争優位性を確立するために自社内での開発やカスタマイズを重視し、他社との差別化を図る必要があります。
例えば、 IT サービス業界やデジタルプロダクトを展開している企業などは、内製化によって自社のニーズに最適化された技術を柔軟に導入できるため、迅速な改善や変更が可能になります。また、高度なスキルを保有するエンジニアが社内に在籍していれば、効率的に内製化プロジェクトを進められるため、内製化のパフォーマンスを最大化できます。
さらに、長期的な視点で社内の成長やスキルの底上げを図りたい企業にとっても、内製化は大きなメリットをもたらします。こうした企業では、エンジニアの育成や技術の蓄積が企業の成長に直接的に貢献するため、外部リソースに頼らないことで得られる戦略的な効果も期待できます。
内製化が向いていない企業
一方、内製化が向いていない企業の代表例としては、コア業務に注力したい企業や、 IT 部門に多くのリソースを割けない企業などが挙げられます。例えば、専門知識を要する業務が多岐にわたる場合、内製化にかかる時間やコストが負担になることがあります。
このタイプの企業では、内製化によってプロジェクトが遅延したり、日常業務に悪影響を及ぼしたりする可能性があるため、システムの開発・運用は外部のパートナー会社に任せたほうが効率的だと言えるでしょう。また、急速な技術進化に対応しづらい企業や、必要な人材を確保しづらい状況にある企業に関しても、内製化はハードルの高い取り組みになります。
このように、内製化をすべきか否かは自社が置かれている状況に応じて変わります。まずは、多角的に自社の現状把握を行い、内製化によるメリット・デメリットを十分に考慮したうえで、慎重に検討を進めることが大切です。
内製化を実現するための 5 ステップ
内製化を行う際には、適切な手順でプロジェクトを進めていく必要があります。最後に、内製化を実践する際の流れについて、 5 つのステップに分けてわかりやすく解説します。
Step.1 目的の明確化と要件定義
なぜ内製化を進めるのか、その目的を明確化することが内製化プロジェクトの第一歩です。例えば、コスト削減や競争優位の確保、技術力の社内蓄積など、内製化の狙いを設定し、具体的な要件を定義します。これにより、プロジェクトの方向性が定まり、関係者間の理解も深まります。
Step.2 プロジェクトの体制構築と人材確保
次に、内製化を進めるためのプロジェクト体制を構築します。社内のリソースを検討し、必要であれば新たにエンジニアを採用するなど、プロジェクトを推進するうえで必要となる人材を確保します。この時、内製化の経験が豊富な人材をリーダーに任命することで、プロジェクトのスムーズな進行が期待できます。
Step.3 開発環境の整備と IT ツール導入
内製化を進めるためには、効率的な開発環境と適切な IT ツールの導入が必要不可欠です。例えば、プロジェクトチーム内のコミュニケーションを円滑化するグループウェアや、ナレッジ共有を効率化するコラボレーションツールなど、必要なツールを整備し、チーム全体がスムーズに作業できる環境を構築することが大切です。これにより、開発の質とスピードが向上し、結果として内製化プロジェクト成功への近道になります。
Step.4 開発プロセスの設計と運用
開発環境を整備し、必要な IT ツールを導入した後は、開発プロセスの設計や運用ルールの設定などを行います。この時、内製化プロジェクトの全体進捗を見える化できるよう、進捗管理や品質管理に関しても明確なガイドラインを策定することが大切です。このように、事前設計を慎重に行ってから運用フェーズに移行すれば、計画的かつ円滑に内製化を進めることが可能になります。
Step.5 継続的な PDCA サイクルの実践
システムが完成に近づいたら、リリースの前にテストを行うことが重要なポイントになります。機能テストやセキュリティテストなどを実施し、問題が発見された場合は改善を重ねていきます。そして、リリース後も継続的な運用改善を行い、 PDCA サイクルを回し続けることで、内製化による成果を最大化できます。
関連記事:システム内製化とは?具体的なメリットや成功させるための戦略をわかりやすく解説!
まとめ
本記事では、内製化のメリット・デメリットや内製化が向いている企業、向いていない企業の特徴など、あらゆる観点から一挙にご説明しました。
企業がシステム内製化を実現することで、開発速度の向上やセキュリティの強化など、様々なメリットを享受できます。この記事を読み返して、重要なポイントを理解しておきましょう。
G-genは、Google Cloud のプレミアパートナーとして Google Cloud / Google Workspace の請求代行、システム構築から運用、生成 AI の導入に至るまで、企業のより良いクラウド活用に向けて伴走支援いたします。
サービスを見る
サービス資料をダウンロードする
無料で相談する
本記事を参考にして、システムの内製化を検討してみてはいかがでしょうか?
Contactお問い合わせ

Google Cloud / Google Workspace導入に関するお問い合わせ